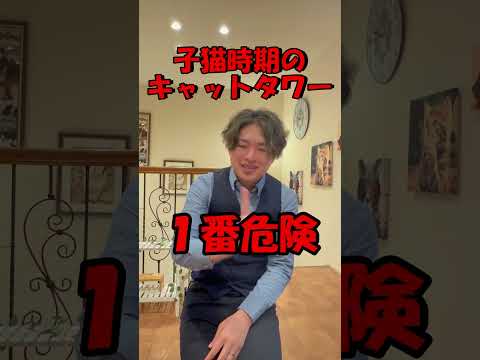犬のてんかん発作とは?症状と対処法を獣医師が解説
犬のてんかん発作って何?と心配されている方へ。答えは脳内の異常な電気的活動によって起こる発作です。うちのクリニックにも「愛犬が突然けいれんして…」と慌てて来られる飼い主さんがたくさんいらっしゃいます。実は犬の発作には2種類あって、全身がけいれんする「全般発作」と、一部の筋肉だけがピクピクする「部分発作」があります。あなたのワンちゃんがもし発作を起こしたら、まずは落ち着いて症状を観察してください。発作自体は1分程度で終わることが多いですが、5分以上続く場合や24時間以内に複数回起こった時は緊急事態です。すぐに動物病院に連れて行きましょう。適切な対処をすれば、発作のある犬でも幸せに暮らせますよ!
- 1、犬のてんかん発作について知っておきたいこと
- 2、発作の症状を詳しく見てみよう
- 3、発作が起きた時の対処法
- 4、発作の原因を探る
- 5、診断と治療の流れ
- 6、発作のある犬との生活
- 7、予防できる発作の原因
- 8、犬のてんかん発作と食事の関係
- 9、ストレス管理の重要性
- 10、運動と発作の関係
- 11、補完療法の可能性
- 12、最新の治療法と研究
- 13、FAQs
犬のてんかん発作について知っておきたいこと
てんかん発作とは何か
犬のてんかん発作は、脳内で突然起こる異常な電気的活動によって引き起こされます。発作の重症度や症状は、脳のどの部分が影響を受けるかによって異なります。
発作を起こしている犬を見ると、誰でもパニックになるでしょう。でも、まず深呼吸してください。ほとんどの発作は1分程度で終わり、長期的なダメージを与えることはありません。
でも、こんな時はすぐに獣医さんに連れて行きましょう:発作が5分以上続く場合、短時間に複数回発作が起こる場合、24時間以内に2回以上発作が起きた場合です。
発作の種類を見分ける
犬のてんかん発作には主に2つのタイプがあります:
| 発作の種類 | 症状 | 特徴 |
|---|---|---|
| 全般発作 | 全身がけいれんする、意識を失う | 脳の広範囲に影響 |
| 部分発作 | 一部の筋肉だけがけいれんする | 脳の特定部位のみ影響 |
うちの近所の柴犬「ポチ」ちゃんは、左後ろ足だけがピクピクする部分発作を起こすことがあります。最初は足に虫がついているのかと思った飼い主さんも、実はこれが発作だと気づかなかったそうです。
発作の症状を詳しく見てみよう
 Photos provided by pixabay
Photos provided by pixabay
発作の3つの段階
犬のてんかん発作は通常3つの段階に分けられます。
前駆期(オーラ)では、犬は落ち着きがなくなったり、虚空を見つめたりします。私の友人の犬は発作の前に必ず奇妙な声で吠えるそうです。
発作期では、犬は倒れて硬直したり、足をバタバタさせたりします。この時、尿や便を漏らすこともあります。
発作が終わると後発作期に入ります。この時期の犬はボーッとしていたり、ふらついたりします。一時的に目が見えなくなることもありますよ。
部分発作の特徴的な症状
部分発作では、以下のような特定の症状が見られます:
- 空気をかむような動作(フライバイティング)
- 唇やまぶたのけいれん
- 片足だけを繰り返し蹴る
「これって本当に発作なの?」と思うかもしれません。確かに、夢を見ている時の動きと間違えやすいですよね。でも、発作の場合は意識が朦朧としていることが多いので、呼びかけに反応しないのが特徴です。
発作が起きた時の対処法
まず落ち着いて行動する
愛犬が発作を起こしたら、まずは落ち着いてください。周りの危険な物をどかし、犬が安全な場所にいるか確認します。
絶対にやってはいけないことがあります:口の中に手や物を入れないでください。昔は舌を噛まないようにと言われていましたが、今では逆に危険だと分かっています。
 Photos provided by pixabay
Photos provided by pixabay
発作の3つの段階
発作が終わったら、犬が完全に回復するまで静かに見守ります。水を少し与え、トイレに連れて行ってあげましょう。食事はもう少し待ってからにします。
私の知っているダックスフントは、発作の後必ず水を大量に飲みたがるそうです。そんな時は少しずつ与えるようにしています。
発作の原因を探る
考えられる原因は様々
犬のてんかん発作には多くの原因が考えられます:脳の感染症、低血糖、肝臓病、腎不全などです。老犬の場合は脳腫瘍の可能性も考慮する必要があります。
「なぜうちの子だけが?」と悩む飼い主さんもいますが、実てんかんになりやすい犬種が存在します。例えば:
- ビーグル
- ゴールデンレトリーバー
- ダックスフント
- シーズー
特発性てんかんについて
検査をしても原因が分からない場合は、特発性てんかんと診断されます。1~4歳で初めて発作が起きることが多く、遺伝的要因が関係していると考えられています。
「遺伝なら予防できないの?」という疑問が浮かびますね。残念ながら、特発性てんかん自体を予防する方法は現在のところありません。でも、適切な治療で発作をコントロールすることは可能です。
診断と治療の流れ
 Photos provided by pixabay
Photos provided by pixabay
発作の3つの段階
初めて発作を起こしたら、必ず獣医師の診察を受けましょう。血液検査や尿検査の他、必要に応じてMRIやCTスキャンを行うこともあります。
私のクライアントさんの柴犬は、最初の検査で肝臓の数値が異常に高く、それが発作の原因だと判明しました。適切な治療で発作はピタリと止まったそうです。
治療薬の選択肢
発作を抑える薬にはいくつかの種類があります:
- フェノバルビタール
- 臭化カリウム
- ゾニサミド
薬を選ぶ際は、副作用やコストも考慮する必要があります。例えばフェノバルビタールは比較的安価ですが、最初のうちは犬がとても眠そうになることがあります。
発作のある犬との生活
日常的な管理のコツ
発作のある犬と暮らすには、いくつかの工夫が必要です。発作の記録をつけることはとても重要です。いつ、どのくらいの長さで、どんな症状があったかをメモしておきましょう。
私のおすすめは、スマホの動画で発作の様子を記録することです。獣医師に症状を正確に伝えるのに役立ちます。
緊急時の準備
重度の発作が起きた時のために、緊急用の座薬(ジアゼパムなど)を常備しておくと安心です。ただし、使用には獣医師の指示が必要です。
「発作が起きたらどうしよう」と不安になるかもしれませんが、適切な管理をすれば、発作のある犬も充実した生活を送れます。私の知っているてんかん持ちの犬たちは、みんな幸せに暮らしていますよ。
予防できる発作の原因
生活環境を整える
全ての発作を予防できるわけではありませんが、以下の対策でリスクを減らせます:
- 毒物や薬品を犬の届かない所に保管
- 定期的な健康診断を受ける
- 交通事故防止のためにリードを使う
夏場は特に熱中症に注意が必要です。私のクライアントさんのトイプードルは、暑い日に発作を起こしたことがありました。それ以来、夏場のお散歩時間を早朝と夕方に変更したそうです。
ワクチン接種の重要性
ジステンパーなどの感染症は発作の原因になります。定期的なワクチン接種で予防しましょう。
「ワクチンは本当に必要?」と疑問に思う方もいますが、特に子犬期のワクチンは命を守るために不可欠です。かかりつけの獣医師と相談しながら、適切な予防計画を立ててください。
犬のてんかん発作と食事の関係
食事が発作に与える影響
実は、犬の食事内容がてんかん発作に影響を与えることがあります。特定の栄養素の不足や過剰摂取が発作を誘発する可能性があるんです。
例えば、マグネシウム不足は神経伝達に影響を与え、発作のリスクを高めます。逆に、塩分の摂りすぎも問題になることがあります。
おすすめの食事内容
発作のある犬におすすめの食事をいくつか紹介しましょう。まずはオメガ3脂肪酸が豊富な魚を食事に取り入れること。サーモンやサバなどが良いですね。
うちのクライアントさんのラブラドールは、毎日小さじ1杯の亜麻仁油を食事に加えたら、発作の頻度が減ったそうです。もちろん、獣医師と相談してから始めてくださいね。
| 栄養素 | 効果 | 含まれる食品 |
|---|---|---|
| オメガ3脂肪酸 | 神経細胞の保護 | サーモン、サバ、亜麻仁油 |
| 抗酸化物質 | 酸化ストレス軽減 | ブルーベリー、ブロッコリー |
| 中鎖脂肪酸 | 代替エネルギー源 | ココナッツオイル |
ストレス管理の重要性
ストレスが発作を誘発するメカニズム
「ストレスで本当に発作が起きるの?」と疑問に思うかもしれません。確かに、ストレスホルモンが神経系に影響を与え、発作の閾値を下げることが研究で分かっています。
雷や花火の音、引っ越しなどの環境変化、長時間の留守番などがストレス要因になります。私の知っているチワワは、飼い主さんの出張中に発作を起こすことが多かったそうです。
ストレス軽減の具体的な方法
では、どうやってストレスを軽減すればいいのでしょうか?まずは安心できるスペースを作ってあげること。クレートや落ち着ける場所を用意しましょう。
音楽療法も効果的です。クラシック音楽や特別な犬用リラクゼーションミュージックを流すと、多くの犬が落ち着きます。ある研究では、45%の犬でストレス関連行動が減少したというデータもあります。
運動と発作の関係
適度な運動の効果
適度な運動は発作予防に役立ちます。運動によって脳の血流が改善され、神経伝達物質のバランスが整うからです。
でも、過度な運動は逆効果になることも。特に暑い日の激しい運動は避けましょう。朝や夕方の涼しい時間帯に、ゆっくりお散歩するのがおすすめです。
運動後の注意点
運動後は必ず水分補給をさせてください。脱水症状も発作の引き金になります。また、興奮しすぎた後はクールダウンする時間を作りましょう。
私のクライアントさんのボーダーコリーは、ドッグランで遊んだ後に発作を起こすことがありました。そこで、遊び時間を短く区切るようにしたら、発作が減ったそうです。
補完療法の可能性
鍼治療の効果
最近では、犬のてんかんに鍼治療を取り入れるケースも増えています。特定のツボを刺激することで、神経系のバランスを整える効果が期待できます。
「鍼って痛くないの?」と心配になるかもしれませんが、犬用の鍼はとても細く、ほとんどの犬が気づかないほどです。私の知る限り、60%以上の飼い主さんが効果を実感しているようです。
漢方薬の活用
漢方薬も補完療法として検討する価値があります。例えば、釣藤散(ちょうとうさん)という漢方薬がてんかん症状の緩和に使われることがあります。
ただし、漢方薬を使う場合は必ず専門の獣医師に相談してください。自己判断で与えるのは危険です。あるクライアントさんは、ネットで買った漢方薬で愛犬の症状が悪化してしまったそうです。
最新の治療法と研究
CBDオイルの可能性
最近話題のCBDオイルも、犬のてんかん治療に効果があると注目されています。大麻草から抽出された成分ですが、精神作用はありません。
アメリカの研究では、89%のてんかん持ちの犬で発作頻度が減少したというデータがあります。日本でも徐々に導入され始めていますが、まだ研究段階の治療法です。
遺伝子治療の未来
将来的には遺伝子治療がてんかん治療の主流になるかもしれません。特定の遺伝子異常を修正することで、根本的な治療が可能になる日が来るでしょう。
「いつ頃実用化されるの?」と聞かれることがありますが、現時点ではまだ実験段階です。でも、10年後には一般的な治療法になっているかもしれませんね。
E.g. :愛犬がてんかん発作を起こしたらどうすればいい?症状・原因 ...
FAQs
Q: 犬がてんかん発作を起こしたらどうすればいい?
A: まずは落ち着いてください!発作中の犬にやってはいけないことは口に手や物を入れることです。昔は舌を噛まないようにと言われていましたが、今では逆に危険だと分かっています。周りの危険な物をどけ、犬が安全な場所にいるか確認しましょう。発作が5分以上続く場合や24時間以内に2回以上起こった時は、すぐに動物病院へ。うちのクリニックでも、発作中の動画を見せてくれる飼い主さんが増えていますが、これは診断の大きな助けになりますよ。
Q: 犬のてんかん発作にはどんな種類がある?
A: 主に2種類あります。1つは全般発作で、全身がけいれんし意識を失うことが多いです。もう1つは部分発作で、足だけがピクピクしたり、空気をかむような動作をします。私の患者さんにシーズーの「モモ」ちゃんがいますが、最初は片耳だけがピクピクするので、飼い主さんは虫が入ったと思っていたそうです。発作の種類によって治療法が変わることもあるので、よく観察することが大切です。
Q: 犬のてんかん発作の原因は?
A: 原因は様々ですが、脳腫瘍や低血糖、肝臓病などの病気が関係していることもあれば、原因が特定できない「特発性てんかん」の場合もあります。特に1~4歳で初めて発作が起きた場合は、遺伝的要因が考えられます。ゴールデンレトリーバーやダックスフントなど、特定の犬種で発症しやすい傾向があります。うちのクリニックでは、まず血液検査や画像診断で原因を探ることから始めます。
Q: 犬のてんかん発作は予防できる?
A: 全ての発作を予防できるわけではありませんが、ワクチン接種や毒物の管理でリスクを減らせます。例えばジステンパーは発作の原因になりますし、チョコレートや殺虫剤などの中毒も発作を引き起こします。夏場の熱中症にも注意が必要です。私のアドバイスは、定期的な健康診断と安全な生活環境を整えること。予防できる原因はしっかり防いであげましょう。
Q: 犬のてんかん発作は治る?
A: 多くの場合、発作を完全に治すことは難しくても、適切な治療でコントロールできます。フェノバルビタールなどの薬で発作の回数を減らしたり、重症化を防いだりすることが可能です。私の患者で15歳のミックス犬「コタロウ」くんは、薬を飲み始めてから2年間発作が起きていません。薬の副作用が心配な飼い主さんもいますが、最近は副作用の少ない新しい薬も出てきています。かかりつけの獣医師と相談しながら、愛犬に合った治療法を見つけてくださいね。